2027年、介護保険制度の見直しから考えるこれからのケア
こんにちは、「ゴーヤの知恵畑」へようこそ!
今日のテーマはちょっと真面目に、「介護の未来」についてです。
2027年に予定されている介護保険制度の見直し。
その中で大きなポイントとなっているのが、
- ケアプランの有料化
- 要介護1・2の「地域支援事業」への移行
- 介護サービスの自己負担割合の見直し
この3点です。
介護は、誰にとっても他人事ではありません。
家族や自分自身の将来に関わる重要なテーマ。
「なんとなく不安…」「よくわからないまま」ではなく、
いまのうちにきちんと知って、備えておきましょう!
ケアプランが「有料」に?
専門職の力をどう評価するのか
現在、ケアマネジャーが作成してくれるケアプラン(介護サービス計画書)は、原則無料です。
これは介護保険制度によって全額給付されているためです。
ところが、2027年の制度見直しでは「自己負担導入」の議論が進んでいます。
国が検討している案では、1割程度の自己負担が導入される可能性があります。
🥒 ゴーヤ先生の豆知識
「ケアプラン」は、ケアマネジャーがご本人やご家族の生活状況、希望をヒアリングして立てる“生活の設計図”のようなものなんじゃ!
本来、とても専門性の高い仕事なんじゃよ〜!
一見すると少額負担に思えますが、毎月発生する費用ですし、
経済的な不安のある方には大きな心理的ハードルになることも。
また、負担が導入されることでケアプランの利用控えが起きれば、
結果的に介護の質が低下してしまう懸念もあります。
要介護1・2は「地域支援事業」へ?
軽度者が“制度の外”に出される可能性
現在、要介護1・2の方も介護保険サービスを利用していますが、
今後はこれらの方を「地域支援事業」に移行させようという議論があります。
これは簡単にいうと、市区町村主体の支援に切り替えるということ。
「地域の助け合い」「ボランティア」「NPO」「住民による互助」などが中心になります。
狙いは、介護保険の財政を守ること。
しかし、移行によって懸念されているのは、
- 利用できるサービスの「質」と「量」が下がる
- 地域によって格差が生まれる
- 現場が混乱し、介護疲れが増す
といった問題です。
🥒 ゴーヤ先生の豆知識
「要介護1・2」は一番“在宅介護”が必要な時期なんじゃよ〜。
ここで地域の力が問われることになるんじゃ!
介護サービスの負担割合が増える?
介護サービスを利用する際、現在の自己負担割合は以下のようになっています。
- 原則1割負担(所得によっては2〜3割)
ところが、制度維持のために「2割負担の対象を拡大する」案が出ています。
特に年金収入や資産が一定以上ある高齢者は、将来的に一律2割負担になる可能性も。
とはいえ、介護は一度始まると月に数万円〜十数万円かかるケースもあります。
そこに負担が増せば、「施設に入れない」「訪問介護が頼めない」などの問題が深刻化します。
介護保険制度の今後に必要な視点とは?
このように、2027年の見直しでは「財政の持続可能性」が重視されており、
制度のスリム化や地域分権が進もうとしています。
しかし、介護は人の「暮らし」や「尊厳」に直結するものです。
制度だけでなく、以下のような視点も同時に必要です。
- 家族の介護離職を防ぐ社会整備
- 多世代が関われる地域づくり
- 介護職の待遇改善と人材育成
- ICTやAIの活用による効率化
また、「自分ごととして準備する姿勢」も大切です。
ゴーヤ先生のひとこと🍀
🥒「未来の介護は“他人まかせ”では乗りきれんぞい!
若いうちから情報を集め、暮らしに“介護の視点”を入れておくとええんじゃ!」
まとめ|介護の未来は「私たち」でつくるもの
2027年の介護保険制度の見直しは、
今後の介護の在り方に大きな影響を与える分岐点となるでしょう。
制度の縮小が進む一方で、
「地域」「家族」「当事者」がそれぞれに備え、
声を上げていくことが求められています。
最後にもう一度お伝えしたいのは、
介護は決して「老後になってから考えるもの」ではない、ということ。
いま、この記事を読んでいるあなたが、
「未来の介護を考える第一歩」を踏み出してくれたことを、心から応援します!
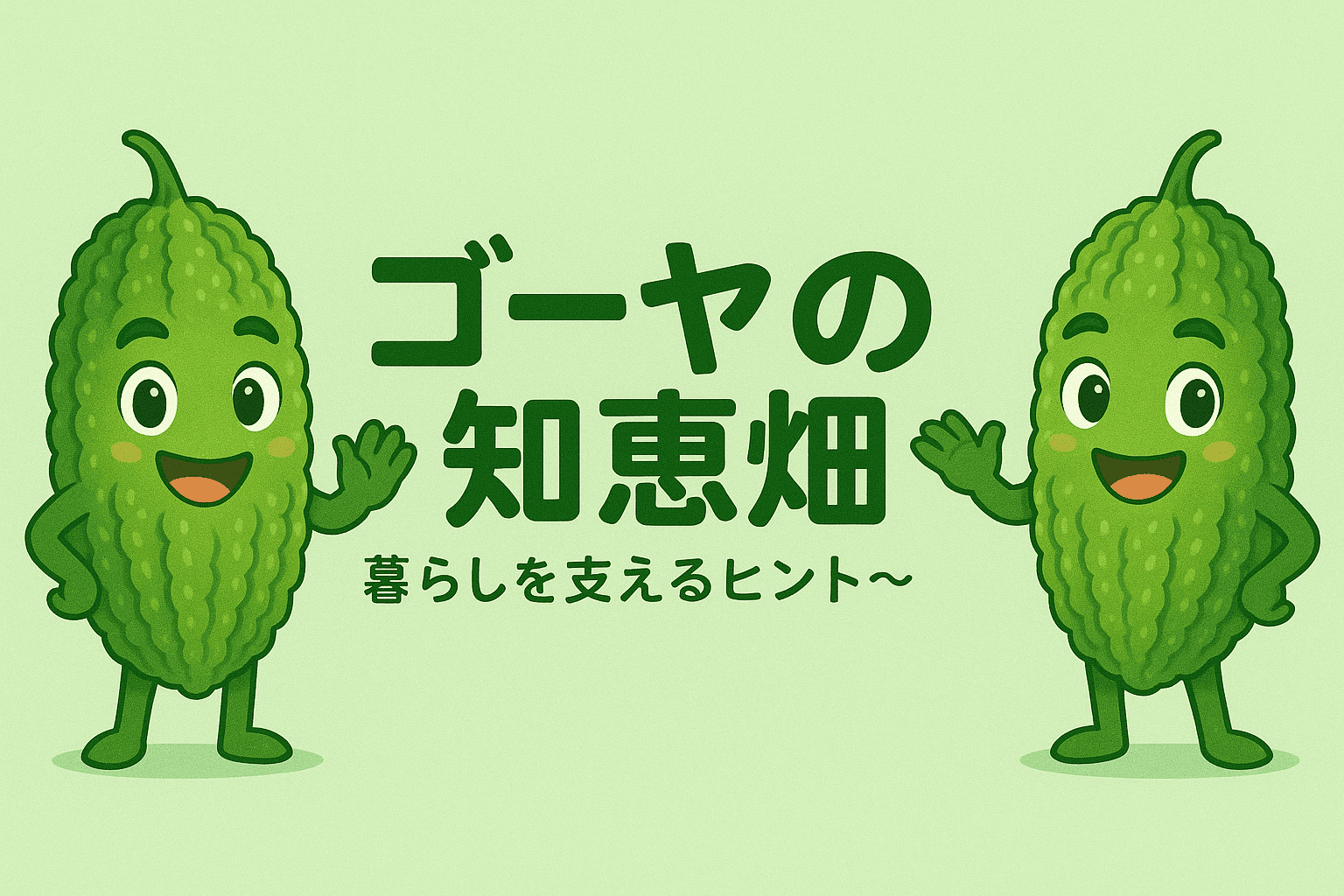
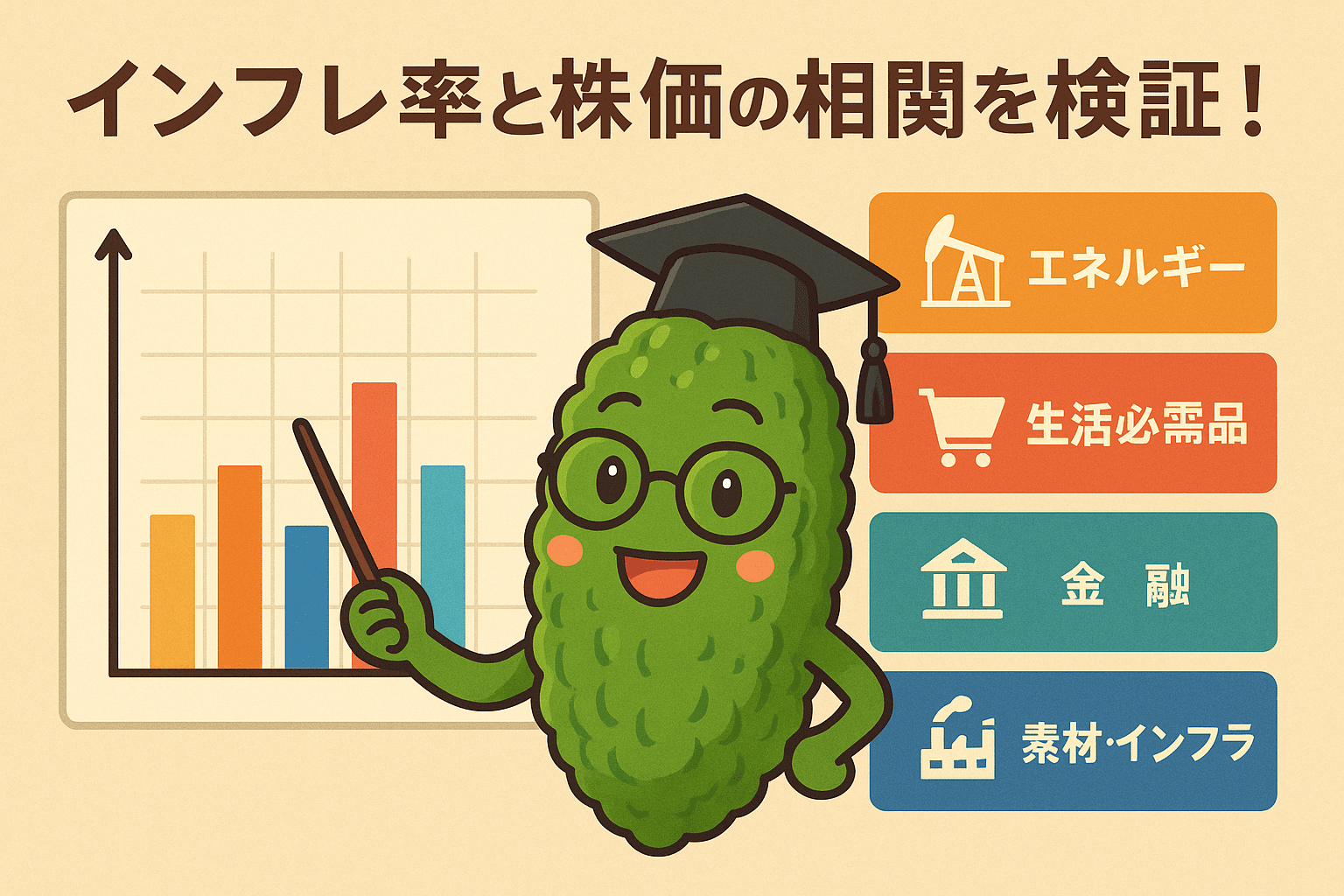



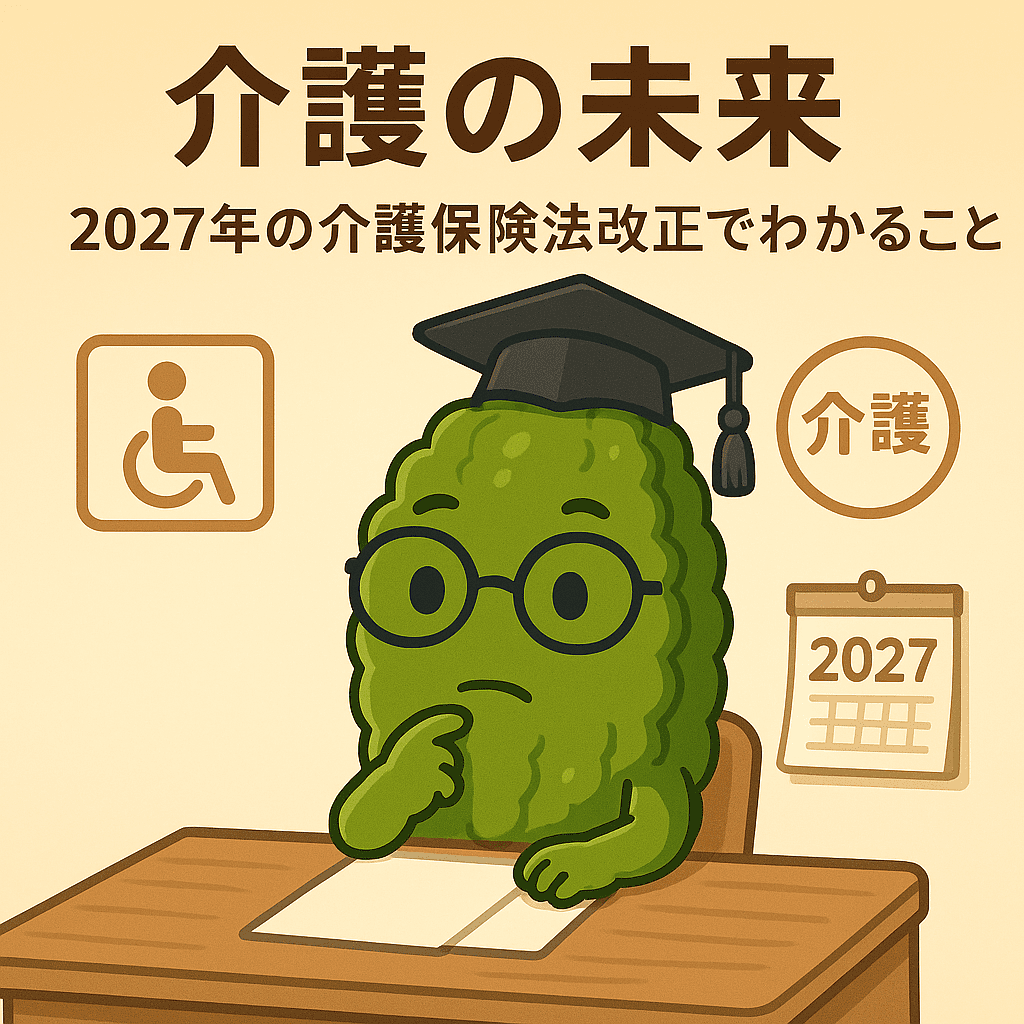
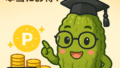

コメント